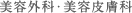院長ブログ
Diary of Gifu Skincare Clinic
2019.04.06
コンタクトレンズ装着は眼瞼下垂発症のリスクです。なぜ?
先日、笠松にある松波総合病院にて、健やかネットワークのセミナーがありました。この日のテーマは「眼瞼下垂」と「形成外科のできること」でした。眼瞼下垂は形成外科疾患の中でも大変ポピュラーな疾患で、ある程度治療方法も確立されています。しかし、更なる手術方法の改良や、基礎医学(神経生理学)的な研究も進化しつつある、興味深い分野です。
松波総合病院形成外科部長の北澤先生のご講演を拝聴し、面白かったことを備忘録として記したいと思います。
眼瞼下垂の症状について
自覚症状として、まぶたの開けづらさや重い感じ、上方視野の悪化、まぶしい感じ、二重の乱れや目の上のくぼみ、眉毛の挙上、おでこのしわの悪化、そして、頭痛や肩コリ等々・・・これらは教科書的に言われる症状です。そこにもう一つ、あごを挙げてしまうということを示されました。専門用語でいうと項部をやや後屈し、下顎が挙上された状態で、眼瞼が挙がっていないから、眼球を下方視ぎみにして見てしまうということでしょう。眼瞼下垂の肩こりについては、眉毛を挙げてしまうため、前頭筋から帽状腱膜さらに僧帽筋まで緊張してしまうからと理解しておりましたが、項部後屈した姿勢はさらに僧帽筋の循環を悪くし肩が凝ってしまうのだろうということでした。このことは、臨床写真からもよくわかることで、術後の顔写真は鼻の穴が目立たないのに対し、術前は眼瞼下垂状態のため項部を後屈しているので鼻の孔が丸見えになっているのです。
厚ぼったい一重で、目つきが悪そうな方って眼瞼下垂なのでしょうか。
このような患者さんが二重術を目的に来院されますが、よく見ると睫毛は黒目にあたっており、正面視でも瞳孔中心がギリギリ見えるぐらいなんてことがあります。このような方に視野検査をすると、上方視が悪いという客観的な検査結果が出るそうです。眼瞼下垂の一つの症状です。当院でもこのような方の手術を行うと、視野が明るくなった、上の方が見やすくなった、など、よい結果になることが多く、おまけに目がパッチリして見た目の雰囲気も良くなったように感じていただくことが多いです。逆さ睫毛もきょうせいすることができます。
コンタクトレンズは眼瞼下垂症発症リスクです。
ハードコンタクトレンズを長年装着している方に眼瞼下垂が発症しやすいと言われます。この理由として、レンズを外す際、まぶたを強く外側へ引っ張ったりします。腱膜性眼瞼下垂は瞼板と挙筋腱膜の接合部のゆるみなのですが、この動作により、早くこのゆるみを誘発してしまうのではないかと言われます。私もそう思い込んでおりました。重度のアトピー性皮膚炎や花粉症で目をよくこする癖がある人も、物理的な力の反復により、ゆるみが生じるのでしょう。
ハードレンズの外し方は下まぶたを使う方法やスポイトを使う方法などあり、術後はこのような方法にしましょうと説明しています。しかし、一日一回の引っ張る動作ぐらいで下垂が誘発されるのかという疑問と、外し方は下まぶたで取ってるという人もいかにもコンタクトレンズによる下垂という症状でみえる方もいます。どうやら・・・
ハードコンタクトレンズのような厚みのある固いものを装着し、瞬きを繰り返していると、薄い結膜とその次の層にあるミューラー筋や挙筋腱膜が徐々に菲薄化してくるようです。腱膜性眼瞼下垂は瞼板と挙筋腱膜の接合部のゆるみといいますが、確かに挙筋腱膜も非常に脆弱化しているように感じます。ハードほどではないですが、ソフトレンズでも同様です。ハードレンズ装着者の眼瞼下垂発症は20倍高く、ソフトレンズで8倍、また、ハードレンズ装着歴27年以上の人は27年以下に比べて11倍の高リスクとなると、教えていただきました。
術後にコンタクトレンズをやめていただけるのは良いことですが、無理な方は、装着時間をいかに短くするかが、再発予防に重要なことと言えます。
松波総合病院のホールが会場でした。
カテゴリ:眼瞼下垂